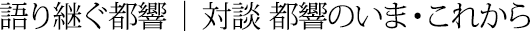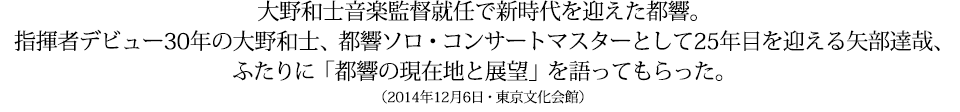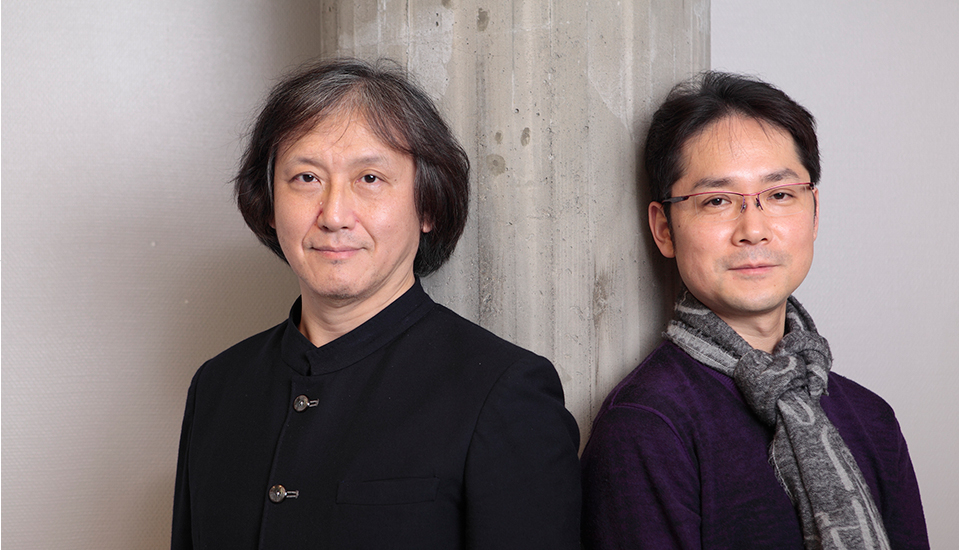
司会・進行:国塩哲紀(都響芸術主幹) まとめ:荒井惠理子
変わってきた都響
―大野さんが指揮者デビューされたのが1984年3月、都響のファミリーコンサートでした。
その後1990年9月の「大野和士都響指揮者就任披露演奏会」で、コンサートマスター・デビューされたのが矢部さんです。
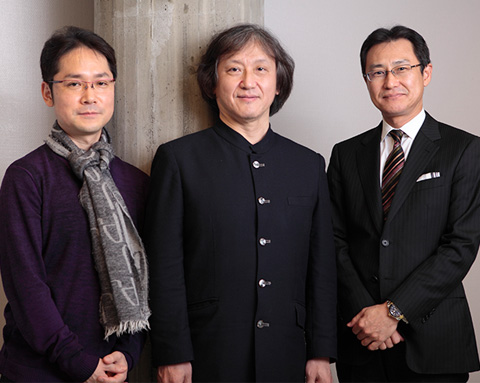
左から矢部達哉氏、大野和士氏、国塩哲紀氏
矢部
25年前ですね。期せずして同じ日に都響との関わりを始めた2人として、舞台で紹介されたんです。池辺晋一郎先生の交響曲第5番と、ラベック姉妹とのプーランク、そしてバルトークの《管弦楽のための協奏曲》。それが僕の最初の定期でした。
大野
1990年の定期のことはよく覚えていますよ。都響の委嘱作である池辺先生の新作を初演させていただくということでとても名誉に思いましたし、頬を紅潮させて“オケコン”の練習に臨んだのを思い出します。都響の定期演奏会に初めて出たのは1989年3月でしたが、その時は非常に緊張しました。ショスタコーヴィチの6番でしたが、最初の練習の日の朝、「はっ」と目が覚めて、電車に揺られながら「どうしよう、どうしよう」と。東京文化会館の廊下で楽員さんに「どうしたの? あがってるの?」と声をかけられたくらいですから、誰の目にも緊張していることが分かったのでしょう。
―以来ずっと第一線で活躍されているなかで、都響をはじめ、日本のオーケストラの変化を感じることはありますか?
大野
日本のオーケストラは近年、急速な変化を遂げて、いま成熟した時期に来ていると思います。これまで日本のオーケストラについて海外で言われてきたのは、「技術的に正確で、短時間に曲をまとめることができるが、内容の深みに欠ける」というような評価だったと思いますが、例えばきょうリハーサルしたフランツ・シュミットやバルトークの難曲などいろいろなプログラムをやり続けてきた結果、自分たちの体のなかに蓄積されてきたものが、大変厚みのあるものになって演奏に反映されてきていると思います。それによって、核になる古典的なレパートリーもはっきり見えてくるようになったと思いますね。
矢部
僕の実感としては、お互いに聴き合って室内楽的に弾くことに関して、25年前と比べると格段の進歩を感じます。僕が入団した頃に、若手や中堅だった先輩方がずっと積み重ねてきた努力の賜物ですし、ソロが上手ということだけではなく、室内楽的に洗練されたセンスを持ったメンバーがたくさんそこに加わってくれました。すごく良いチームになりました。1990年9月の定期でやったバルトークのオケコンは、僕自身経験がなかったこともあって非常に難しく、リハーサルも本番もものすごく大変だったのです。けれど、何年か前に大野さんであらためてこの曲を演奏した時に、以前感じていた困難さがほぼオールクリアで、最初の練習の時から、音楽に踏み込めるという感触がありました。
きょう練習したシュミット、バルトークもとりわけ難しい曲ですが、練習2日目で、音楽的により高いところを目指そうという姿勢をみなが共有して大野さんと対峙するということができるようになったのは、25年の変化かなという気がします。
大野さんは、集中力が一気に高まると、別世界の人に見えるんですよね。自分たちに見えないものが見えている、感じられないものが感じられているのではないかと思うことが、何回もありました。「大野さんの指揮で聴くと、作曲家の顔が見える」と言っていた人がいるのですが、本当にそうで、作曲家の声、心に近付こうという姿勢を演奏していて常に感じます。

大野
作曲家と語り合えるくらい近くなりたいという気持ちは、いつも強く持っています。シュミットでいえば、彼がウィーン宮廷歌劇場のオーケストラのチェリスト時代、音楽監督だったマーラーがいつも彼を指名したんですって。『ドン・ジョヴァンニ』のツェルリーナとの二重唱などチェロが重要な曲があると、首席チェロがいるにもかかわらず、トップサイドのシュミットにソロを弾かせたと。チェロだけでなく、シュミットはピアノの教授でもあった。そういうような豊かな音楽的バックグラウンドが封じ込められたのが4番のシンフォニーで、そこに彼の才能の集積を見ることができるわけです。そういうことに非常に喜びを覚えますし、それを楽員と共有することができるのも嬉しい。楽員と分かち合うことによって、聴衆にも伝えられるわけですから。
都響の“伝統”とは?
―いま大野さんがおっしゃった音楽の捉え方は、長年ヨーロッパやアメリカで活躍されるなかで体験されたこと、自然に感じられてきたものからの影響もありますか?
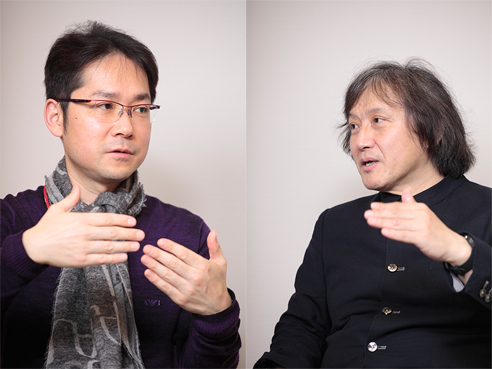
大野
これはアメリカのオーケストラを指揮した時に感じたことなのですが、ハンガリー舞曲で、「タターン」「タリラー」と頭にアクセントのあるフレーズを演奏している時、オーセンティックというか、音楽が生まれた国からしか出てこないような音がどこからか湧き起こってくることがあった。後で聞いたら、マジャール人のお祖父さんを持つ奏者がいるという。あるいはヴェルディの序曲で、極めて陽気にリズムを刻むヴァイオリンのおじさんがいて、その人がリトル・イタリーの出身だったり。そういうふうにアメリカでも、2、3世代前をたどると、作曲家が暮らした時代、風土に関係のある人たちがオーケストラのなかにいたりするわけです。そういう時、ふっと作曲家を身近に感じましたし、自分を作曲家の道に導いてくれたきっかけの一つになったことは間違いないですね。
日本の事情はもちろん違いますが、これまで共演した名指揮者やソリストたちが、オーケストラに光を与え続けてくれ、それが楽員一人一人のなかに集積して、いまより一層の光彩を放つようになってきたといえるのではないかと思います。
矢部
その実感はすごくあります。例えば、ベルティーニさんとマーラー・ツィクルスをやっていた時と今とでは、メンバーが相当入れ替わっているんですね。これだけ入れ替わってしまったら、せっかくベルティーニさんと築いたことが一からやり直しになってしまうのではないかと思ったことがあったのですが、新しく入ってくる人たちが、ほのかに残るDNAみたいなものを感じて自分のものにしていくのを見て、ああ、オーケストラの伝統というのはこうやって途切れずに受け継がれていくものなのかなと思いました。
ベルティーニさんでいえば、分岐点というか、「このオーケストラが認められたかもしれない」と僕が思った瞬間があるんです。ベルティーニさんとマーラー10番の第1楽章《アダージョ》を2度目にやった時、彼が誰にも聞こえないくらいの独り言で「彼らは本当によく分かっている。私自身より前回のことを覚えているかもしれない」と言った時のことです。彼はすごく厳しい人で、「自分は種を蒔くために来た」とよく言っていましたけれど、ちょっと花が咲いたのを、そこで見つけたのではないかなと。その時、もしかしたら僕らは違う段階に行けるかもしれないと思ったのを覚えています。
指揮者というのはとても大きな存在で、例えばペーター・マークさんでシューマン、メンデルスゾーンをやった時、フルネさんでドビュッシー、ラヴェルをやった時、不思議なほど生き生きとした音楽になったことがあって、あっと思ったのを覚えています。そして、彼らがいなくなった後でも、その蓄積は僕らのなかに生きているんですよね。フルネさんが亡くなって随分経った後でも、あの時の響きがイメージとしてどこかに残っていて、また新しい指揮者がそこに何かをプラスする、というかたちになっているような気がします。マーラーにしても、今の都響のマーラー・スタイルというのがあって、そこに新しく共演する指揮者がアイディアや今までスコアから見過ごしてきたことを指摘してくれる。どのオーケストラでもそうだと思いますが、そういう積み重ねをこれからもしていくのだろうなと。
やはり50年も経つと、そういう守るべき伝統があって、同時に捨てなければいけない悪しき習慣もあるわけで、そうしたことを新しい指揮者と見つけていくのは、オーケストラで弾く楽しみでもありますね。
音楽的な“抵抗”を忘れてはいけない
―そうした“都響の伝統”は、どのように演奏に活きるのでしょう?

大野
昔からある特徴の大きな一つは、柱がしっかりしているということですね。コントラバスのセクションをはじめ、骨組みがしっかりしている。それは立体像を作る上でとてもプラスになる点です。その伝統が若い世代にも受け継がれて、今の都響を支えていると思います。
また今の特徴としては、世代間バランスが大変いい。若手、中堅、ヴェテランのバランスが、一人一人が培ってきたものがプラスとなって表れるような、アクティヴな状態になっている。理想的と言っていいと思いますね。
矢部
若手のことをいえば、いまの音楽学校の弦楽器のレヴェルはおそろしく高いので、都響に限らずこれからどんどん優秀な人材がオーケストラに入ってくると思います。いまやオーケストラは狭き門で、ヴァイオリン1人の募集に70人くらいの応募が来るんですよ。随分変わったなと思うのは、僕が学生の時には、オーケストラに入るのは「セカンド・ベスト」みたいな感じがあったのです。何よりもソリストが一番偉くて、ソリストになれない人がオーケストラに入るみたいな。僕は全然そうじゃなくて、高校生の時からオーケストラをやりたくて仕方なかった。ベスト・チョイスとしてオーケストラに入ったわけですが、いまや時代がそういう状況になりつつあって、とても優秀な学生で「オーケストラに入るのが目標」という人が結構多くなっています。とても嬉しいし、これからどんどん技術的水準が上がっていくのは間違いないと思いますね。
反面、その弊害もあって、柔軟性というのは、オーケストラにとってマイナスにもなり得るんです。僕は「言われたことがぱっとできればOK」というような風潮は良くないと思っていて、指揮者に何か言われたら、「はいそうですか」とすぐ応えるのではなく、その意味をもっと考えるべきだと思っているんですね。考えた結果、「こう解釈する」と消化した上で演奏しなければ、本当の意味での相乗効果は得られないと思うのです。
―そうでなければ何日間もリハーサルをする意味がありませんからね。
矢部
そうなのです。かつてジャーヴィスさんというコンサートマスターが都響にいらして、僕は5年くらい一緒に弾かせていただいて本当に感謝しているんですけれど、彼から聞いた話で印象的だったのが、ショルティやハイティンクから「あなたは指揮に合わせ過ぎる。自分をフォローしないでくれ」と言われていたということ。当時の都響では、指揮者に合わせる傾向が強かったのですが、ジャーヴィスさんはいつも「自分たちの考えがあった上で、指揮者の解釈や方向性を受け入れるべきだ」と強調されていました。ジャーヴィスさんが言っていたのはこういうことだったのかなと、実感として分かるようになったのは最近のことですが。
まず一人一人の音楽があって、それを100%出した上でのアンサンブルであるべきなんです。合わせなくちゃいけない、遅れちゃいけないと考えるのではなく、個人の音楽を表現した上で、まとめあげるのがコンサートマスターや首席奏者の役割だと思いますから。自分を捨てて他に合わせるというのは、ある意味、楽なことです。そうではなくて、ある種の“抵抗”――反抗ではない抵抗――、音楽的な「んっ」という何かがあるべき。1回目のリハーサルでバンと合ってしまって、これ以上何やるの? となったら何の広がりもない。まず「できた」と思うところからその先に進む過程のなかで、音楽が創られていくわけですから。
その点でも、大野さんのリハーサルは、作曲家が何を求めているのか、何を思ってこの曲を書いたのか、を考えながら音楽を作り上げていく共同作業ができて刺激的なんです。
大野
私は、作曲家に近づくポケットをより多く持っていたいですし、オーケストラにもそれを共有してほしいと常に思っているんですね。例えばシュミットの作品をやるとしたら、彼が生きたウィーンに流れていた音、彼の奥様がユダヤ人だったこと、そしてマーラーという巨人の功績を音楽言語として持っていたこと……、すべてを踏まえてリハーサルに臨みたいと思っています。マーラーという作曲家も、マーラー以後の未来、あるいはマーラー以前を考えることに意味がある。彼が指揮者としてコンサートで古典の楽曲を復活させたこと、後期のシンフォニーで、未来を志向する音楽のあり方を示したことを含めて捉える必要があると思います。
―マーラーのお話が出ましたが、歴代の音楽監督や首席指揮者にマーラーの得意な指揮者が多かったためか、都響はおそらく日本で最も多くマーラーを演奏してきたオーケストラです。都響の伝統にはそのことも影響しているでしょうか?
矢部
マーラーは、表現の多彩さ、音色の変化などオーケストラ音楽のすべてが求められる作曲家ですから、ツィクルスでじっくり取り組めたことが、都響の財産になっているのは確かだと思います。個々の曲でいうと、都響は2番や8番など大掛かりなものが多く、9番は意外と少ないんですが。いずれも非常に難しい作品ですので、楽員一人一人が責任を持っていい演奏をしようと取り組んだ結果、表現の幅が広がり、オーケストラ全体のレヴェルの向上につながったのは間違いないですね。マーラー演奏に評価の高い都響の音楽監督の歴史に大野さんを迎えて、新たに都響のマーラー演奏を築いていくことができるのを、とても楽しみにしています。
大野
将来的には、ポスト・マーラーの作曲家たち、あるいは古典的な作曲家たちというプリズムを通しながら、あらためてマーラーをやるというかたちになってくるのではないでしょうか。その時々にマーラーを演奏し続けていくかたちにできればと思います。
これから都響が目指すこと、求められること
―これからの都響が目指すべき方向などについてお感じになっていることをお聞かせください。
矢部
レパートリーがより新しく洗練されたものになっていくだろうと想像しています。これまでやらなかった曲に出会う機会も多くなってくるでしょう。そうした時、都響をこれまで聴いてくださってきた方々、新しく都響を聴いてくださる方々、すべてを含めた聴衆のみなさんと新しいレパートリーを共有して、より一層の成長に繋げていけたらいいなと思います。そうやってチャレンジする曲が、本当に価値のあるものなのか、そうでないのかのジャッジメントをするのは、聴衆の方々かもしれない。「こんな曲に出会えて良かった」と思っていただけるように、「新しい伝統」を刻んでいけたらと思います。
大野
そのためにも、どの時代の作品だろうと、私はもっとスコアの深い読み手でありたい。スコアに書かれたことを自分のなかに映し、都響とともに音楽にしていきたい。

矢部
少し個人的な希望も述べさせてもらえれば、大野さんは欧米でオペラを多く指揮なさっているので、一緒にオペラをやってみたいという気持ちはすごくあります。もちろんできればピットのなかで。あるいはバレエ、特に《春の祭典》を、例えばNoismのような優れたバレエカンパニーと上演するなどということが実現したら、都響の歴史にまた新しいページが加わると思います。
あと、大切なのは聴衆の層を広げることですね。オーケストラを育てるのは何と言っても聴衆ですから、クラシック人口が減っていくのは僕らにとって深刻な問題です。子どもたちがクラシックに触れる機会を多く作りたい。オーケストラはダイナミクスの幅も広くインパクトがあるので入門にふさわしいと思いますし、大人数が真剣に弾く姿は子どもにもダイレクトに伝わるのではないかと思うのです。何より子どもたちから受けるエネルギーは僕らにとって刺激になります。
大野
都響が年間約60回行っている「音楽鑑賞教室」はもちろん、私自身が直接子どもたちと交流できる「マエストロ・ビジット」、さらに今後はサントリーホールと港区による港区の小学4年生を対象としたプロジェクトに、都響とともに参加します。「初めて聴いたオーケストラが都響で、それで音楽が好きになった」という人をもっと増やしたいですね。
矢部
最後にあらためて強調したいのは、いまこのタイミングで都響の音楽監督に大野さんを迎えられることが、我々にとって望外の喜びであるということです。これまで都響を訪れたさまざまな指揮者のもとで経験を積んできた僕らが、50年の節目を迎えて新しく踏み出そうという時に、最良の方を迎えることができたと思っています。これからますます、いい演奏をしていきたいと思います。