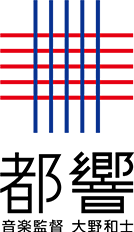楽員紹介 - 都響について

第2ヴァイオリン
高田はるみ (たかだはるみ) Harumi TAKADA
(1989年3月1日入団)
東京芸術大学音楽学部卒業、同大学院修士課程修了。海野義雄、故田中千香士、原田幸一郎の各氏に師事。東京文化会館推薦新人演奏会、日演連推薦新人演奏会などに出演。1989年、東京都交響楽団に入団。ソロ、室内楽にも取り組み、2011年より姉と「Duo SORELLE 」として毎年リサイタルを行っている。また、バロック・ヴァイオリン奏者として、「オーケストラ・リベラ・クラシカ」、「バッハ・コレギウム・ジャパン」でも活動している。
私の音楽はじめて物語

スズキ・メソードは曲を聴いて、耳で覚えて弾くことが中心ですが、私は姉の音を聴いていたからか、最初のうちはスムースに進みましたね。才能教育研究会の全国大会で大勢で弾いた時、私は最前列に居て目に留まったらしく、視察にいらしていたオイストラフが抱きしめて、頭を撫でてくれた。自分では全く憶えていないのですが、光栄だったなと思います。
ただ、子どものころは身体が弱く、よく学校を休んでいましたし、レッスンも半年くらい中断したことがありました。それで、先生には専門的にやるのは難しいかな、と言われていました。
小5から上条尚人(ひさと)先生に替わり、スズキ・メソードではやったことがなかったスケールや練習曲ばかりのレッスンになり、1年間、曲を全然やらせてもらえずびっくり。練習曲もそれなりに面白かったですが。そのころ、名古屋青少年交響楽団というジュニア・オーケストラに入り、渡邉暁雄さんの指揮で《フィンランディア》をやったりしました。それまで一人で練習していたのとは全然違って、いろいろな楽器の中で弾くのが楽しくて。これがオーケストラの原体験だった気がします。
ヴァイオリンはずっと続けたくて、中2のころ愛知県立明和高校音楽科の受験を決めました。とはいえ、身体が弱くてプロになるための練習を続けてこなかったので、受験に失敗したらヴァイオリンは趣味に留めようかなと、私立は普通科を受けたんです。
幸いにも明和高校に合格。大学も地元で、と思っていたのですが、高校の担任の先生が東京藝大の受験を勧めてくださって。話を決めてからは、すごく練習したと思います。海野義雄先生が名古屋に月に1回ほどいらしていたので、高2からレッスンを受け、音程、リズム、音色などを改めて鍛えられました。
東京藝大へ進み、藝祭のオーケストラで弾いた《ニュルンベルクのマイスタージンガー》前奏曲やバルトーク《管弦楽のための協奏曲》が思い出に残っています。室内楽ではベートーヴェンの弦楽四重奏曲第12番をルイ・グレーラー先生に熱心にレッスンいただいたことが印象的ですね。
大学院に進み、初めてエキストラへ行ったのが都響で、コシュラーさん指揮の
ヤナーチェク《グラゴール・ミサ》でした。それから常連エキストラのような形で弾かせていただき、88年3月に大学院を修了、同年春のヨーロッパ演奏旅行にも参加。その後、オーディションを受けて入団し、最初の定期演奏会もコシュラーさん指揮の《わが祖国》(全曲)で、何だか縁を感じましたね。
若杉弘さんの時代で、私は入団からの2年でマーラーの交響曲を全曲弾きました。大人数で一つの音楽を作り上げる体験は格別ですし、一方で友人たちと弦楽四重奏をやり、古楽を弾く機会もある。ヴァイオリニストとして幸せなことだなと思っています。
(『月刊都響』2014年5月号 取材・文/友部衆樹)