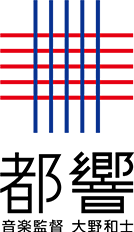【インタビュー記事】指揮者 ローレンス・レネス (第935回定期演奏会Aシリーズ)
ニュース

2018年9月以来、2度目の都響登場となるマルタ系オランダ人のローレンス・レネスさん。実は大の親日派で、ヴァイオリンを学んでいた10代には、縁あって関西学院交響楽団のオランダ公演に参加、さらに指揮者の中田昌樹氏に招かれ、2ヶ月ほど日本に滞在した経験もあるそうだ。その時の友人たちが、今でも日本での演奏会に駆けつけてくれるのだという。また、オランダで故・岩城宏之氏の指揮マスタークラスを受講したこともあり、日本との結びつきを大切にしてきた。今回は14日間の隔離期間を経ての定期への出演となるが、都響と再び共演できることにくらべたら隔離など些細なこと、と公演への意気込みを語ってくれた。
写真:関西学院交響楽団を指揮するレネス(中央)と、中田昌樹氏(右)
——前回の都響との共演の印象はいかがでしたか?
レネス:オーケストラと初めて共演する時は、お互いのケミストリーがうまくいくだろうかといつもちょっぴり緊張しますが、都響との初顔合わせはとても手応えがあり、印象深いものでした。あの時は直前に亡くなられたオリヴァー・ナッセンの代役でしたので、オーケストラにとっても聴衆にとっても敬愛するナッセンの代わりにまったく未知の人が現れたわけですからね。ナッセンの曲と武満の《オリオンとプレアデス》、そしてホルストの《惑星》という、オーケストラの力量を存分に発揮できるプログラムで、楽しく音楽を作り上げることができたと思います。聴衆もとても心を開いて熱心に聴いてくださったように感じました。今回、再び招いていただいて光栄ですし、とても嬉しく思っています。

——今回の曲目についてお聞かせください。ワーグナーの『さまよえるオランダ人』序曲に続いて、松田華音さんの独奏でプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番、そしてメインにプロコフィエフの交響曲第5番という構成ですね。
レネス:当初はサリー・ビーミッシュのヴィオラ協奏曲第2番が組まれており、私にとっても初めての曲でしたので意気込んで準備しておりましたが、残念ながらソリストのタベア・ツィンマーマンさんが来日できなくなりました。代わりに、有望なピアニスト松田華音さんとプロコフィエフを一緒に演奏できることをとても楽しみにしています。
プロコフィエフは私にとって大切な作曲家のひとりです。私が15歳の頃、オランダ国立ユース・オーケストラでヴァイオリンを弾いていた時にプロコフィエフのバレエ音楽《ロメオとジュリエット》を演奏したのですが、思春期まっただ中だった私に、この音楽が新しい世界を開いてくれたことを覚えています。そして今回演奏する彼の交響曲第5番は、このバレエの世界にとても近いと思います——たとえば第3楽章の愛の主題や、戯れるような終楽章など。《ロメオとジュリエット》交響曲と呼んでもよいぐらいです。聴衆の皆さんも、きっと情熱的な旋律や、胸がしめつけられるような不協和音とそれに続く美しさに圧倒されることでしょう。交響曲の形式は取っていますが、冒頭の一つの旋律から壮大なストーリーが紡ぎ出されていくさまは魔法のようであり、それをオーケストラと一体となって皆さんとシェアできればと思います——パンデミックの今だからこそ殊更に。
——ワーグナーの『さまよえるオランダ人』序曲は、当初演奏されるはずだったビーミッシュの協奏曲の副題が《船乗り》であるというつながりで選曲されたのだと思いますが、レネスさんはオペラ指揮者としても長く活躍してこられたので、これまでにワーグナーもたくさん指揮されてきたのでしょうか?
レネス:オペラ指揮者としては、スウェーデンの王立歌劇場の音楽監督を2012から5年間務めましたし、そのほかにも欧米の歌劇場に客演し、ワーグナーのほぼ全ての作品を複数回指揮してきました。
実は私はセーリングが趣味で、この夏マルタからイタリアやギリシャをめぐるヨットの一人旅をしたのですが、ある晩、ひじょうに大きな嵐に見舞われました。怖くはなかったのですが、嵐の原始的なパワーに畏怖の念を抱きました。そしてこの時の体験はまさに『さまよえるオランダ人』序曲の世界に通じると感じました。この曲は単に荒波や吹きすさぶ風の描写ではなく、こうした自然への畏怖の感情を表しているのだと私は思います。

——レネスさんは、コロナ禍前は世界中を飛び回ってオーケストラを客演していらっしゃいましたが、この一年半はどのように過ごされていましたか?
レネス:パンデミックの中で唯一良いことがあったとすれば、生活がスローダウンし、自分の内なる声に耳を傾けられるようになったことでしょうか。日々に忙殺される中で見失っていましたが、改めて大事なことだと感じています。
私自身はこの一年半、指揮の仕事はほとんどありませんでした。今年の春にコンセルトヘボウで無観客のコンサートが1つあり、7月にオーストラリアのメルボルン交響楽団で2つの演目を指揮したぐらいです。たいへん苦しい時期でした。なぜなら、私にとって音楽とは究極的には人々と分かち合うものだからで、その機会を奪われたことが何よりもつらかったのです。
もちろん家でスコアを読んでいる時も頭の中では音楽は鳴っていますが、それはオーケストラの皆さんと一緒に音楽を作り上げるのとはまったく別のものです。コロナ禍では、さまざまなオンライン配信の試みもありましたが、でもやはりコンサートホールで感じるエネルギー、それはオンラインやCDでは代替できない体験だと確信しています。

——レネスさんは音楽院を卒業後、オランダ放送フィルでエド・デ・ワールト氏のアシスタントを務めました。今でもとても親しくされているとうかがっています。彼から一番学んだことは何でしたか?
レネス:彼からは本当に多くのことを学びました。入念に準備すること、勤勉であること、自分に忠実かつ正直であること、そして奏者たちによく耳を傾けること——この最後がいちばん重要なことかもしれません。
これは今まで誰にも語ったことがないのですが、私が若い頃、とあるオーケストラの音楽監督を務めていた時に関係がうまくいかなくなったことがありました。それでエドに相談したら、「君はオーケストラのことをよく知っているけれど、間違いばかりに気をとられていて、音楽を指揮することを忘れている。一人ひとりの奏者たちが紡いでいる音楽のストーリーに耳を傾けなさい」とアドバイスしてくれました。その言葉にはっと気づかされたのでした。エドとは今では友人として、同僚として毎週のように連絡を取り合っています。
——今後のご予定は?
レネス:このあとオランダに戻り、10月9日にコンセルトヘボウでオランダ放送フィルとの演奏会があります[インターネットラジオで生中継あり]。敬愛するJ.アダムズの《チェアマン・ダンス》、録音もしているシュレーカーの『はるかな響き』から《夜曲》、R.シュトラウスの《ドン・ファン》に加え、世界初演の三重協奏曲と、盛りだくさんのプログラムです。オランダもようやく先日より会場の収容人数が100%に戻りました。
——最後に都響のファンおよび聴衆へのメッセージをお願いいたします。
レネス:都響ファンの皆さんにお伝えしたいのは、これほど惜しみなく与えてくれるすばらしいオーケストラを持っているということはとても喜ばしいことです。同時に、これほど熱心で忠実な聴衆を持つ都響も幸せだと思います。こうした困難な時代だからこそ、お互いを支え、愛し、気遣ってほしいと思います。本拠地でのオーケストラと聴衆の関係こそ何よりも大切なものなのです。
(9月17日 取材・聞き手:後藤菜穂子)