Essay


イェルク・ヴィトマン~対立する要素を両立させる豊かな音楽性
小室敬幸 Takayuki KOMURO(作曲・音楽学)
はじめに
英国の大手音楽WEBメディア『bachtrack』の調査によれば、存命中の(クラシック及び現代音楽系の)作曲家のなかで、2023年に作品が演奏された回数を集計したところ、第3位にランクインしたのがイェルク・ヴィトマン(1973年6月生まれ/51歳)だ。ちなみに第1位がジョン・ウィリアムズ、第2位がアルヴォ・ペルト、第4位がトマス・アデス、第5位がフィリップ・グラス、第6位がジョン・アダムズ……という錚々たる顔ぶれのなかでの3位なのである。現代音楽の現役作曲家のなかで、最も成功を収めているひとりがヴィトマンなのだ。
そして彼を語るにあたっては作曲家としてだけでなく、管楽器奏者および指揮者として高い評価を得ているというのも欠かせない。楽器こそ違うがハインツ・ホリガー(1939年5月生まれ/85歳)以来となる存在なのだ。筆者の個人的な体験でいえば、2023年3月13日にトッパンホールで開催された公演において、日本のカルテット・アマービレと共演して彼が吹いたカール・マリア・フォン・ウェーバー(1786~1826)のクラリネット五重奏曲に心底驚かされたことが忘れ難い。同編成の傑作として名高いモーツァルトやブラームスに比べると軽んじられがちなウェーバーだが、ヴィトマンの手によって後期ベートーヴェンとシューベルトに匹敵する作曲家であったのだと痛感させられてしまった。
古楽以後の感覚も持ちながら、場面に応じてロマンティックで濃厚な表現も厭わないのが演奏者・指揮者としてのヴィトマンの特徴といえる。対して、作曲家としてのヴィトマンはどんな存在なのか? 今回、都響が創立60周年記念として他のオーケストラと共に共同委嘱したホルン協奏曲(2023~24)はウェーバーのホルン小協奏曲などの引用を含み、ウェーバーへのオマージュにもなっている。抒情的なメロディやハーモニーが基調なので、この新作だけを聴くと新ロマン主義の作曲家のように思われるかもしれないが、歴代の作品を聴いていくと複合的な要素を併せもつ作風がみえてくる。
そして彼を語るにあたっては作曲家としてだけでなく、管楽器奏者および指揮者として高い評価を得ているというのも欠かせない。楽器こそ違うがハインツ・ホリガー(1939年5月生まれ/85歳)以来となる存在なのだ。筆者の個人的な体験でいえば、2023年3月13日にトッパンホールで開催された公演において、日本のカルテット・アマービレと共演して彼が吹いたカール・マリア・フォン・ウェーバー(1786~1826)のクラリネット五重奏曲に心底驚かされたことが忘れ難い。同編成の傑作として名高いモーツァルトやブラームスに比べると軽んじられがちなウェーバーだが、ヴィトマンの手によって後期ベートーヴェンとシューベルトに匹敵する作曲家であったのだと痛感させられてしまった。
古楽以後の感覚も持ちながら、場面に応じてロマンティックで濃厚な表現も厭わないのが演奏者・指揮者としてのヴィトマンの特徴といえる。対して、作曲家としてのヴィトマンはどんな存在なのか? 今回、都響が創立60周年記念として他のオーケストラと共に共同委嘱したホルン協奏曲(2023~24)はウェーバーのホルン小協奏曲などの引用を含み、ウェーバーへのオマージュにもなっている。抒情的なメロディやハーモニーが基調なので、この新作だけを聴くと新ロマン主義の作曲家のように思われるかもしれないが、歴代の作品を聴いていくと複合的な要素を併せもつ作風がみえてくる。
作曲のはじまり
ドイツのミュンヘンで1973年6月19日に生まれたヴィトマンは、7歳からクラリネットを吹きはじめ、家で盛んに即興演奏をするようになったという。その即興を書き残すために1984年、11歳からカイ・ヴェスターマン(1958~)に作曲のレッスンを受けはじめた。おそらく年齢や経緯からいって、楽典や基礎的な音楽理論を学んだのだと思われる。そして12歳の頃にストラスブールの音楽祭に足を運び、ピエール・ブーレーズ(1925~2016)が率いるアンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏で、クラリネット独奏とテープと電子音響のための《二重の影の対話》(1985年初演)、5人の独奏者とアンサンブルとライヴエレクトロニクスのための《レポン》(1981年初演)を聴き、「官能性」と「色彩の奔流」に衝撃を受けた。
1986年に現在のミュンヘン音楽演劇大学へ入学し、クラリネットを学ぶ。同時に学校のバンドではヤマハの伝説的なシンセサイザーDX7(1983年発売)を弾くようになり、スティングの「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」を何度も聴けるお店で採譜していたという。この世界的ヒット曲は1988年2月1日発売なのでヴィトマンが10代半ばの頃だったのだろう。ところがシンセサイザーを盗まれてしまったため、クラシックの世界に集中する道を選んだ。それでも敬愛し続けているのがジャズのマイルス・デイヴィス(1926~91)で、ヴィトマンは「シェーンベルク、ストラヴィンスキー、ピカソのような革新者です」と語っている。
1986年に現在のミュンヘン音楽演劇大学へ入学し、クラリネットを学ぶ。同時に学校のバンドではヤマハの伝説的なシンセサイザーDX7(1983年発売)を弾くようになり、スティングの「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」を何度も聴けるお店で採譜していたという。この世界的ヒット曲は1988年2月1日発売なのでヴィトマンが10代半ばの頃だったのだろう。ところがシンセサイザーを盗まれてしまったため、クラシックの世界に集中する道を選んだ。それでも敬愛し続けているのがジャズのマイルス・デイヴィス(1926~91)で、ヴィトマンは「シェーンベルク、ストラヴィンスキー、ピカソのような革新者です」と語っている。
作曲の師と弦楽四重奏
ヴィトマンの公式なバイオグラフィでは1994~96年にかけてミュンヘンで、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ(1926~2012)とヴィルフリート・ヒラー(1941~)に作曲を師事したと書かれているが、ヘンツェとの出会いはもう少し早い。ヘンツェが1988年に立ち上げたオペラとムジークテアター(音楽劇)の音楽祭であるミュンヘン・ビエンナーレで、第2回の企画のひとつとして高校生による高校生のための音楽劇というプロジェクトを立ち上げたのだ。そこで白羽の矢が立ったのが当時16歳のヴィトマンで、5場からなる学校オペラ『不在 (Absences)』(休憩なし90分)をヘンツェの支援を受けて書き上げ、1990年5月2日に初演された。現在は作品リストから撤回されているが、ひとつの場面で演奏された弦楽四重奏を抜粋した《『不在』より弦楽四重奏曲(String Quartet from “Absences”)》(1990/93年改訂)は遺されている。
習作とはいえ10代でオペラが初演されたことも凄いが、もっと驚くべきは1993年―つまり本格的にヘンツェやヒラーに習う前だ ! ―に作曲されたクラリネット独奏のための幻想曲(Fantasie)(2011年改訂)、弦楽六重奏のための《1分間に180拍(180 beats per minute)》、クラリネット、ヴァイオリンとピアノのための《ミューズの涙(Tears of the Muses)》(1996年改訂)のいずれもレパートリーとして今も取り上げられていることだろう。《1分間に180拍》は当時流行していたダンス・ミュージックである“テクノ”に触発された作品と作曲者は説明しているが、緊張感のある変拍子と長短調のあいだを揺らぐ旋律はバルトークを思い起こさせる。
そして既に述べた通り、1994~96年にかけてヘンツェとヒラーに習う。日本ではあまり知られていないヒラーだが、調べてみると子ども向けのピアノ小品《バタフライ・ワルツ》が最も有名なようである。彼にとってヴィトマンは最初の生徒だったそうで、この若者にスタイルを押しつけることなく、一緒に視野を広げる手伝いをしてくれた。特に一緒にメシアンのオペラ『アッシジの聖フランチェスコ』の巨大なスコアを読み、ザルツブルク(録音がリリースされている1998年8月の上演だと思われる)へ観に行った体験は、ヴィトマンにとって音楽への考え方を大きく変えるきっかけになったと彼は後年振り返っている。だがこの時代に書き下ろされた作品として、作品リストに掲載されているのはヴァイオリン独奏のための練習曲(Étude)第1番(1995)だけだ。この練習曲は、特殊奏法を含む楽器の可能性を広げるという観点から書かれており、ヴィトマン本人によれば弦楽器の奏法の多くはヴァイオリニストである妹カロリン・ヴィトマン(1976年生まれ)から学んだという。
続いて1997~99年にかけてカールスルーエで、ハイナー・ゲッペルス(1952~)とヴォルフガング・リーム(1952~2024)に師事した時期には、反対に大量の作品が書かれている。ただし、オペラと演劇のあいだに位置するような独自のムジークテアターで有名なゲッペルスの名前は、公式サイトの短いバイオグラフィでは省略されているので、良い関係を築けなかったのかもしれない(ジャンルにとらわれることなく、多彩な音楽を取り入れるゲッペルスはヴィトマン好みな気もするのだが……)。
一方、リームからは多くを学んだようだ。彼が亡くなった際のインタビューでは、マンツーマンのレッスンよりもグループ・レッスンにおいての自由な議論が刺激になったと回顧している。そしてヴィトマンが優れたクラリネット奏者であることを知ったリームは、実質的な協奏曲であるクラリネットと管弦楽のための音楽《線について Ⅱ(Über die Linie Ⅱ)」》(1999)を作曲。その後も20曲以上にわたるクラリネット作品をヴィトマンに提供したことで、師弟を超えた深いやり取りを繰り返した。
この時期には、ヴィトマン本人が創作の中核に位置づけている弦楽四重奏曲の記念すべき第1番(1997)が書かれている。弦楽四重奏コンクールの課題曲として委嘱されたものなのだが、過去の巨匠たちが傑作を遺した分野のため初めての四重奏は挑戦になると前置きした上で、力んでしまって上手く書き始められない。そんな情景を音楽で置き換えるところから始まり、ヴィオラが力ずくで脱出しようとするのだが……。こうした演劇的ともいえる要素はヴィトマン作品でよくみられるし、伝統的な要素との対話もはっきりとした形で作品にあらわれがちだ。
例えば弦楽四重奏曲第1~5番は全5楽章構成に見立てられており、第1番はイントロダクションにあたる。緩徐楽章に相当する第2番《コラール四重奏曲(Chorale Quartet)》(2003)ではハイドン《十字架上のキリストの最後の7つの言葉》、スケルツォ楽章に相当する第3番《狩りの四重奏曲(Hunting Quartet)》(2003)ではシューマンの《蝶々》が参照されている。ゆったりとしたパッサカリア風の楽章である第4番(2005)は具体的な作品名は挙げられていないが、前衛的でノイジーな音色のなかからバロック音楽風の抒情が滲み出している。フィナーレにあたる第5番《フーガの試み(Versuch über die Fuge)》(ソプラノ付き/2005)はベートーヴェンやJ. S. バッハを想起させるフレーズが登場してフーガやカノンを自由に生み出す。そして弦楽四重奏の次なるサイクルである第6~10番(2019~22)では、全てベートーヴェンがテーマになっている。
習作とはいえ10代でオペラが初演されたことも凄いが、もっと驚くべきは1993年―つまり本格的にヘンツェやヒラーに習う前だ ! ―に作曲されたクラリネット独奏のための幻想曲(Fantasie)(2011年改訂)、弦楽六重奏のための《1分間に180拍(180 beats per minute)》、クラリネット、ヴァイオリンとピアノのための《ミューズの涙(Tears of the Muses)》(1996年改訂)のいずれもレパートリーとして今も取り上げられていることだろう。《1分間に180拍》は当時流行していたダンス・ミュージックである“テクノ”に触発された作品と作曲者は説明しているが、緊張感のある変拍子と長短調のあいだを揺らぐ旋律はバルトークを思い起こさせる。
そして既に述べた通り、1994~96年にかけてヘンツェとヒラーに習う。日本ではあまり知られていないヒラーだが、調べてみると子ども向けのピアノ小品《バタフライ・ワルツ》が最も有名なようである。彼にとってヴィトマンは最初の生徒だったそうで、この若者にスタイルを押しつけることなく、一緒に視野を広げる手伝いをしてくれた。特に一緒にメシアンのオペラ『アッシジの聖フランチェスコ』の巨大なスコアを読み、ザルツブルク(録音がリリースされている1998年8月の上演だと思われる)へ観に行った体験は、ヴィトマンにとって音楽への考え方を大きく変えるきっかけになったと彼は後年振り返っている。だがこの時代に書き下ろされた作品として、作品リストに掲載されているのはヴァイオリン独奏のための練習曲(Étude)第1番(1995)だけだ。この練習曲は、特殊奏法を含む楽器の可能性を広げるという観点から書かれており、ヴィトマン本人によれば弦楽器の奏法の多くはヴァイオリニストである妹カロリン・ヴィトマン(1976年生まれ)から学んだという。
続いて1997~99年にかけてカールスルーエで、ハイナー・ゲッペルス(1952~)とヴォルフガング・リーム(1952~2024)に師事した時期には、反対に大量の作品が書かれている。ただし、オペラと演劇のあいだに位置するような独自のムジークテアターで有名なゲッペルスの名前は、公式サイトの短いバイオグラフィでは省略されているので、良い関係を築けなかったのかもしれない(ジャンルにとらわれることなく、多彩な音楽を取り入れるゲッペルスはヴィトマン好みな気もするのだが……)。
一方、リームからは多くを学んだようだ。彼が亡くなった際のインタビューでは、マンツーマンのレッスンよりもグループ・レッスンにおいての自由な議論が刺激になったと回顧している。そしてヴィトマンが優れたクラリネット奏者であることを知ったリームは、実質的な協奏曲であるクラリネットと管弦楽のための音楽《線について Ⅱ(Über die Linie Ⅱ)」》(1999)を作曲。その後も20曲以上にわたるクラリネット作品をヴィトマンに提供したことで、師弟を超えた深いやり取りを繰り返した。
この時期には、ヴィトマン本人が創作の中核に位置づけている弦楽四重奏曲の記念すべき第1番(1997)が書かれている。弦楽四重奏コンクールの課題曲として委嘱されたものなのだが、過去の巨匠たちが傑作を遺した分野のため初めての四重奏は挑戦になると前置きした上で、力んでしまって上手く書き始められない。そんな情景を音楽で置き換えるところから始まり、ヴィオラが力ずくで脱出しようとするのだが……。こうした演劇的ともいえる要素はヴィトマン作品でよくみられるし、伝統的な要素との対話もはっきりとした形で作品にあらわれがちだ。
例えば弦楽四重奏曲第1~5番は全5楽章構成に見立てられており、第1番はイントロダクションにあたる。緩徐楽章に相当する第2番《コラール四重奏曲(Chorale Quartet)》(2003)ではハイドン《十字架上のキリストの最後の7つの言葉》、スケルツォ楽章に相当する第3番《狩りの四重奏曲(Hunting Quartet)》(2003)ではシューマンの《蝶々》が参照されている。ゆったりとしたパッサカリア風の楽章である第4番(2005)は具体的な作品名は挙げられていないが、前衛的でノイジーな音色のなかからバロック音楽風の抒情が滲み出している。フィナーレにあたる第5番《フーガの試み(Versuch über die Fuge)》(ソプラノ付き/2005)はベートーヴェンやJ. S. バッハを想起させるフレーズが登場してフーガやカノンを自由に生み出す。そして弦楽四重奏の次なるサイクルである第6~10番(2019~22)では、全てベートーヴェンがテーマになっている。
管弦楽作品の充実
少し時が進みすぎてしまったので一旦戻ろう。既に触れたように初期作から室内楽では個性を発揮していたのに対し、もう少し編成の大きなアンサンブル作品で作曲者自身が初めて満足することができたのはリームの50歳記念に捧げられた《自由な小品集(Freie Stücke)》(2002)だった。約1~6分ほどの小品が10曲続く作品で、各曲はそれぞれ異なる楽想に基づいているのだが、それぞれの終わりで次の曲へと繋がる要素が挿入される。そうすることで「異質なものが連続する物語」になるのだという。特定のスタイルにとらわれることなく、多彩なサウンドを饒舌に駆使するのがヴィトマンの良さでも弱点でもあったのだが(あるインタビューでヴィトマンは、作曲家としての自らの問題点はアイデアが多すぎることと答えている!)、洗練させる方向も使いこなせるようになり、作曲家としてステップアップしたのであろう。
そして、この頃から管弦楽曲も充実していく。まずは伝統的な声楽ジャンルから得た着想を、声楽なしの大管弦楽で展開した三部作―シューベルトから示唆を受けた《リート (Lied)》(2003/09)、《コアー(Chor)》(2004)、《ミサ(Messe)》(2005)。そして全てが管弦楽曲ではないのだが、答えのない芸術活動をメタファーとして捉えた《迷宮 (Labyrinth)》シリーズ(2005~)―このうち《楽園へ〔迷宮Ⅵ〕(Towards Paradise 〔Labyrinth VI〕》(2021)は実質的なトランペット協奏曲になっている。
協奏的な作品は初期から書かれているが、明確に協奏曲と銘打たれたのはクリスティアン・テツラフが初演したヴァイオリン協奏曲第1番(2007)、ハインツ・ホリガーが初演したオーボエ協奏曲(2009~10)、アントワン・タメスティが初演したヴィオラ協奏曲(2015)、妹カロリンが初演したヴァイオリン協奏曲第2番(2018)だ。タイトルで協奏曲と明示されていないものの、クリーヴランド管の首席フルート奏者ジョシュア・スミスが初演した《フルート組曲(Flûte en suite)》(2011)、ピアニストのイェフィム・ブロンフマンが初演した《葬送行進曲(Trauermarsch)》(2014)もヴィルトゥオーゾをソリストに起用している。シュテファン・ドールが初演したホルン協奏曲も当然そのひとつに位置づけられるわけだ。
そして、この頃から管弦楽曲も充実していく。まずは伝統的な声楽ジャンルから得た着想を、声楽なしの大管弦楽で展開した三部作―シューベルトから示唆を受けた《リート (Lied)》(2003/09)、《コアー(Chor)》(2004)、《ミサ(Messe)》(2005)。そして全てが管弦楽曲ではないのだが、答えのない芸術活動をメタファーとして捉えた《迷宮 (Labyrinth)》シリーズ(2005~)―このうち《楽園へ〔迷宮Ⅵ〕(Towards Paradise 〔Labyrinth VI〕》(2021)は実質的なトランペット協奏曲になっている。
協奏的な作品は初期から書かれているが、明確に協奏曲と銘打たれたのはクリスティアン・テツラフが初演したヴァイオリン協奏曲第1番(2007)、ハインツ・ホリガーが初演したオーボエ協奏曲(2009~10)、アントワン・タメスティが初演したヴィオラ協奏曲(2015)、妹カロリンが初演したヴァイオリン協奏曲第2番(2018)だ。タイトルで協奏曲と明示されていないものの、クリーヴランド管の首席フルート奏者ジョシュア・スミスが初演した《フルート組曲(Flûte en suite)》(2011)、ピアニストのイェフィム・ブロンフマンが初演した《葬送行進曲(Trauermarsch)》(2014)もヴィルトゥオーゾをソリストに起用している。シュテファン・ドールが初演したホルン協奏曲も当然そのひとつに位置づけられるわけだ。
舞台作品
もうひとつ、ヴィトマン作品で重要になってくるのが舞台作品である。先に紹介した学生時代の習作である『不在』(1990)のあと、最先端のバイオテクノロジーとしてのクローン人間を題材とした『鏡のなかの顔(Das Gesicht im Spiegel)』(2002~03/2010)が最初の本格的なオペラとなった。そして『はじまり(Am Anfang)』(2009)と『バビロン(Babylon)』(2011~12)ではどちらも、古代のユダヤ民族が題材になっている。ユダヤ文化への興味は、メンデルスゾーンへの敬愛にも繋がっており、指揮者としてのヴィトマンが大事にレパートリーにしているメンデルスゾーンの交響曲第5番《宗教改革》について、「メンデルスゾーンの胸の中で、ユダヤ教とキリスト教という2つの心臓がどのように鼓動しているかに魅了されている」「メンデルスゾーンがこれらのアイデンティティを互いに対立させるのではなく、すべての愛を持って両方を示していることを、最も美しい方法で見られます」と語っている。
ダイバーシティを体現
対立軸として位置づけられる異なる要素でも、どちらかを選ぶのではなく双方を愛し、音楽上で両立させる。このスタンスはヴィトマン作品の基礎になっているといってよいだろう。過去と現在、保守と前衛、調性と無調……など、ヴィトマンにとっては対立する要素ではないのだ。古くは折衷主義や多様式と称されたアルフレート・シュニトケ(1934~98)なども対立する要素を音楽のなかで共存させたが、無調のなかで明るい長三和音を異なる要素として際立たせたり、伝統的な調性のスタイルのなかに不協和音が混じりこんできたりと異質さが強調されるケースが多い。しかしヴィトマンの場合は《自由な小品集》のように異なる要素が“らしさ”を保ちつつも、繋がっているように聴こえる。
こうしたヴィトマンのスタンスは、現代の多様性(ダイバーシティ)のあり方を体現しているとも捉えられるはずだ。同じような作品を繰り返さず、常に更新していく革新性を大事にしながらも、過去の財産も重要視する。それを矛盾ではなく、豊かさとして表現できるからこそヴィトマンの作品はこれだけ演奏され、評価も勝ち得ているのだろう。
こうしたヴィトマンのスタンスは、現代の多様性(ダイバーシティ)のあり方を体現しているとも捉えられるはずだ。同じような作品を繰り返さず、常に更新していく革新性を大事にしながらも、過去の財産も重要視する。それを矛盾ではなく、豊かさとして表現できるからこそヴィトマンの作品はこれだけ演奏され、評価も勝ち得ているのだろう。
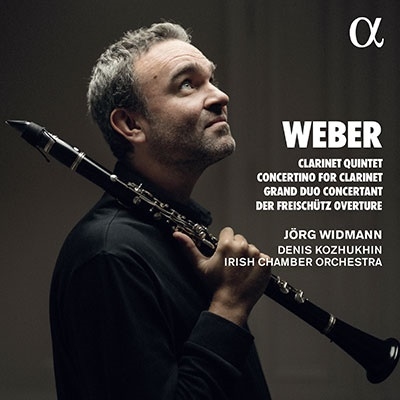
【CD】
ウェーバー:クラリネット小協奏曲/歌劇『魔弾の射手』序曲/協奏的大二重奏曲/クラリネット五重奏曲(クラリネットと弦楽オーケストラ版)
イェルク・ヴィトマン(指揮、クラリネット)
アイルランド室内管弦楽団
デニス・コジュヒン(ピアノ)
〈録音:2016年5月~2019年8月〉
[Alpha, ALPHA637]
*クラリネット奏者としてのヴィトマンを語る上で欠かせないのがウェーバーである。彼が最も親近感を覚える作曲家で、過小評価されている現状を変えたいとまで願っているようだ。収録された小協奏曲、協奏的大二重奏曲、クラリネット五重奏曲(弦楽オーケストラ版)はいずれも技巧性・抒情性に満ちている。指揮している『魔弾の射手』序曲もスマートな名演だ。
ウェーバー:クラリネット小協奏曲/歌劇『魔弾の射手』序曲/協奏的大二重奏曲/クラリネット五重奏曲(クラリネットと弦楽オーケストラ版)
イェルク・ヴィトマン(指揮、クラリネット)
アイルランド室内管弦楽団
デニス・コジュヒン(ピアノ)
〈録音:2016年5月~2019年8月〉
[Alpha, ALPHA637]
*クラリネット奏者としてのヴィトマンを語る上で欠かせないのがウェーバーである。彼が最も親近感を覚える作曲家で、過小評価されている現状を変えたいとまで願っているようだ。収録された小協奏曲、協奏的大二重奏曲、クラリネット五重奏曲(弦楽オーケストラ版)はいずれも技巧性・抒情性に満ちている。指揮している『魔弾の射手』序曲もスマートな名演だ。
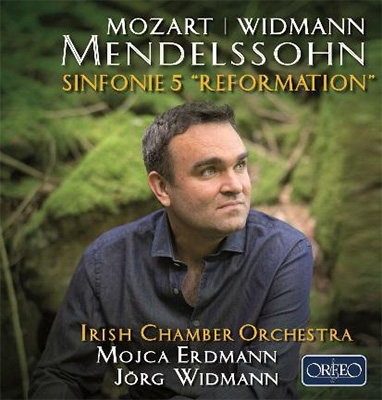
【CD】
モーツァルト:アダージョとフーガ/ヴィトマン:弦楽四重奏曲第5番《フーガの試み》/メンデルスゾーン:交響曲第5番《宗教改革》 他
イェルク・ヴィトマン指揮
アイルランド室内管弦楽団
モイチャ・エルトマン(ソプラノ)
〈録音:2015年4月~2016年12月〉
[Orfeo, C921171A]
*指揮者としてのヴィトマンを語る上で欠かせないのがメンデルスゾーンだ。本文でも触れたように《宗教改革》は彼にとって重要な作品で、第1楽章における古さと新しさの分裂を積極的に見ていくことでメンデルスゾーンの現代性が顕になるという。古い様式とロマン派の様式が混合した本作はヴィトマンの創作姿勢の先駆にあたるのだろう。
モーツァルト:アダージョとフーガ/ヴィトマン:弦楽四重奏曲第5番《フーガの試み》/メンデルスゾーン:交響曲第5番《宗教改革》 他
イェルク・ヴィトマン指揮
アイルランド室内管弦楽団
モイチャ・エルトマン(ソプラノ)
〈録音:2015年4月~2016年12月〉
[Orfeo, C921171A]
*指揮者としてのヴィトマンを語る上で欠かせないのがメンデルスゾーンだ。本文でも触れたように《宗教改革》は彼にとって重要な作品で、第1楽章における古さと新しさの分裂を積極的に見ていくことでメンデルスゾーンの現代性が顕になるという。古い様式とロマン派の様式が混合した本作はヴィトマンの創作姿勢の先駆にあたるのだろう。
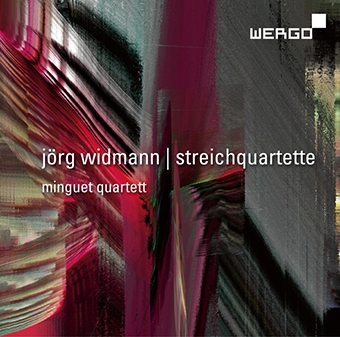
【CD】
ヴィトマン:弦楽四重奏曲第1番/第2番《コラール四重奏曲》/第3番《狩の四重奏曲》/第4番/第5番《フーガの試み》/歌劇『不在』より弦楽四重奏曲/1分間に180拍
ミンゲット四重奏団
クラロン・マクファーデン(ソプラノ)
アレクサンダー・ヒュルスホフ、アンドレイ・シミオン(チェロ)
〈録音:2014年1月、4月〉
[Wergo, WER7316-2](2枚組)
*作曲家としてのヴィトマン入門に最適なのが、彼自身が創作の中核に位置づけている弦楽四重奏だ。本盤には初期作から第5番までを収録。創作の時系列で聴くと彼が作風を確立させていく過程が追え、ノイズと調性の意味を逆転させようとした第2番以降の出来が良い。第3番は人気作だが視覚的要素が大きいので、まずはYouTubeなどで検索を。世界崩壊後に訪れる抒情のような第4番と、崩壊と構築が同時に味わえる第5番はどちらも傑作である。
ヴィトマン:弦楽四重奏曲第1番/第2番《コラール四重奏曲》/第3番《狩の四重奏曲》/第4番/第5番《フーガの試み》/歌劇『不在』より弦楽四重奏曲/1分間に180拍
ミンゲット四重奏団
クラロン・マクファーデン(ソプラノ)
アレクサンダー・ヒュルスホフ、アンドレイ・シミオン(チェロ)
〈録音:2014年1月、4月〉
[Wergo, WER7316-2](2枚組)
*作曲家としてのヴィトマン入門に最適なのが、彼自身が創作の中核に位置づけている弦楽四重奏だ。本盤には初期作から第5番までを収録。創作の時系列で聴くと彼が作風を確立させていく過程が追え、ノイズと調性の意味を逆転させようとした第2番以降の出来が良い。第3番は人気作だが視覚的要素が大きいので、まずはYouTubeなどで検索を。世界崩壊後に訪れる抒情のような第4番と、崩壊と構築が同時に味わえる第5番はどちらも傑作である。
